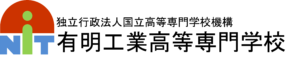目下、お盆休み中です。今年度はカレンダーの関係で、長いです。しかし九州は忘れた頃の梅雨状態で、線状降水帯が思いっきり暴れています。お出かけどころではありません。横殴りに打ち付ける雨が、玄関の隙間から染み込んでくる始末です。猛暑&水不足はどこかに吹っ飛びました。
そんなお盆休みですが、何かとすることはありますし、明けたら学会ラッシュですので、仕事しています。平日は学生さん達の相手で一日があっという間に終わってしまうので(※基本業務ですけどね(^_^;))。休み期間中は落ち着いて自分のしたい仕事ができます。主に研究関係ですね。
さてさて、公の組織にいて不思議に思うことは、コストの概念がないということです。
何か物事を始めようとすると、人手がかかります。コストがかかります。
とかく昨今は、色んな話が次々と振ってきます。変な横文字がついてきて。よくまあ色々考えるなあと。奇抜さを求めるよりも現状のupdateが急務と思うんですがね。そうしないと、予算が取れないんでしょうかねぇ。
研究推進というわりには、スペースは狭いまま。教育推進というわりには、教職員数はそのまま。特別手当とか特別ボーナスなんてものは、基本的にありません。
定額○○ホーダイは、スマホ料金だけにしてくれです。
給与を改善する動きがありますが、現場の者としては、個人云々よりも上記のスペースと数、つまり環境を改善してほしいですね。運転もほどほどにしたいところです。
「箱物は 一度作れば 知らんがな」
視点を変えてみます。例えば、オープンキャンパス。学校の紹介なので、本来は教職員だけで行うべきところかと思います。この国の慣例として、学生達を半ば強制的にボランティア動員します。我が国では、ボランティアの意味が勘違いされています。私、申し訳なさもあってか、一緒に説明しています。でも説明自体は嫌いではありませんので、楽しんでやっています。
公の組織は、各人の良心で保っているなという感がします。こちら、日本国憲法76条ではないんですがね。人材研修は一応ありますが、組織的な人材育成プログラムっていうのはないかなと思います。
良心だけに頼り、精神論を振りかざす運営をしていれば、そりゃ我が国は海外から取り残されますよ。
別の視点から。研究者という人種は基本、個人事業主です。生きるも死ぬも自分次第。では私はそれで生きてこれたかというと、全然そんなことはありません。高名な先生方に恵まれてここまで来られました。運が良かったと思うと同時に、自分の人材育成は基本自分でやってきたなあという感です。
とはいえ、自分の仕事は、自分一人で到底回りません。技術職員さんや事務職員さんの助けがあってこそです。研究も研究室学生達がいてこそです。彼らにとって過剰な負荷を与えてないか、それが彼らのキャリアアップに繋がるか、日々気を遣っているつもりです。はい。
人材は「人財」とも表現されます。しかし「財」の意味って、どれだけの人が分かってるんだろうかと。
Views: 67