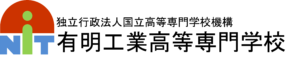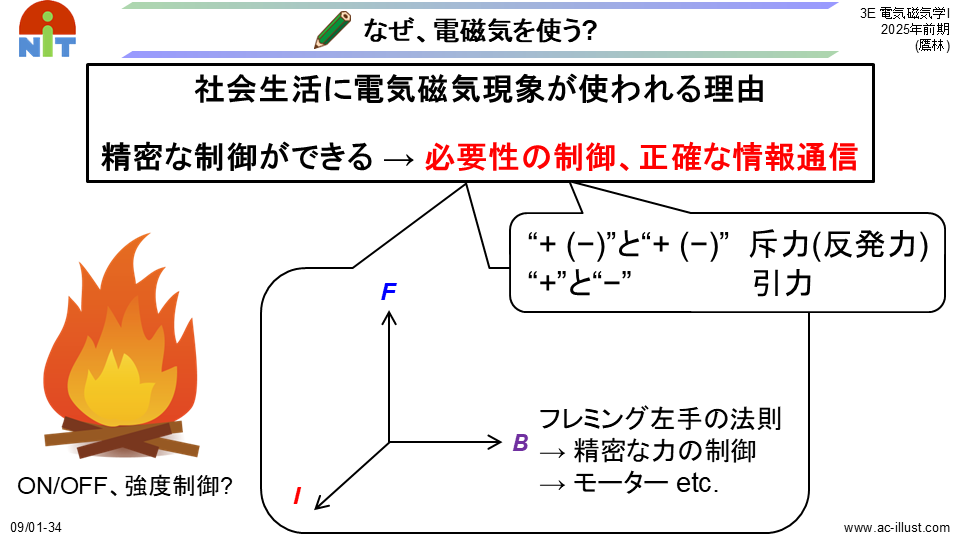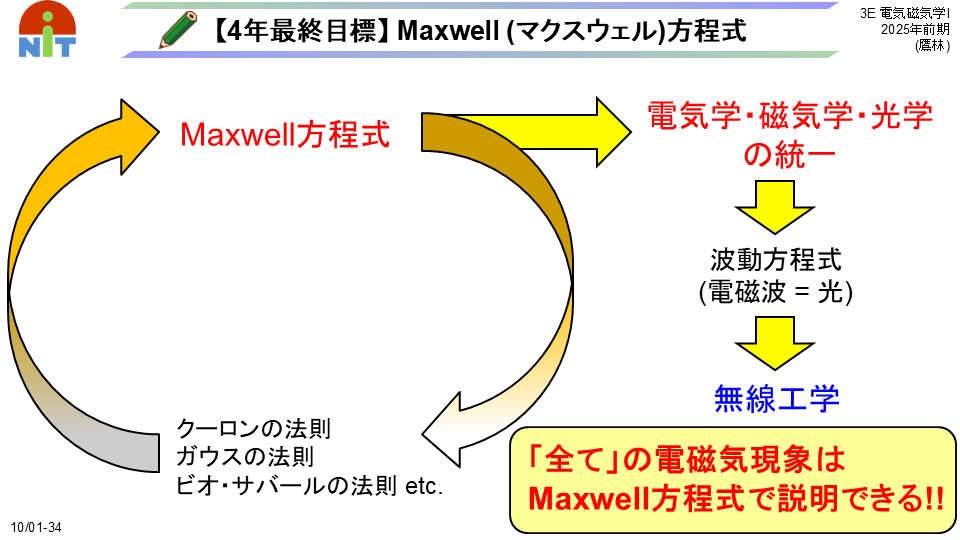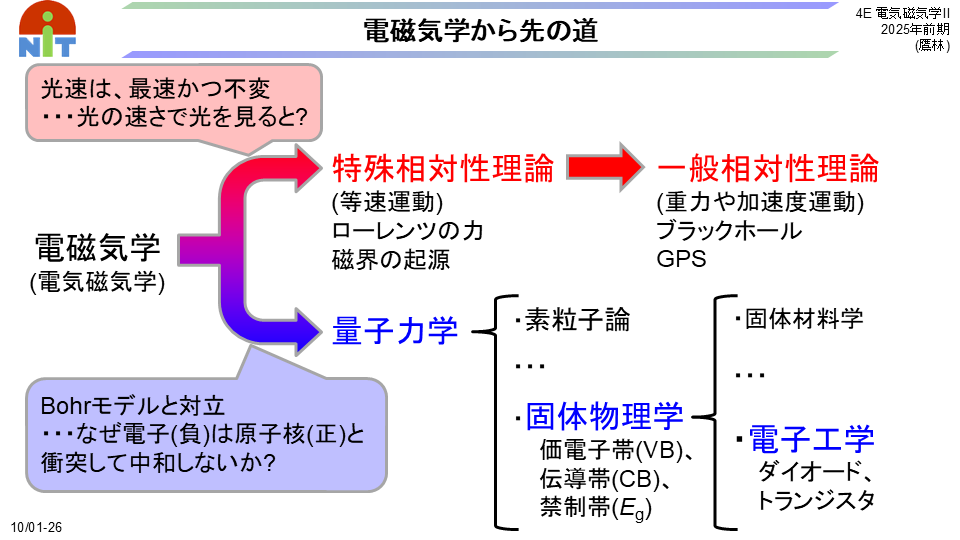今年度も授業が始まりました。毎度授業を実施していく際に最も力を入れていることは、最初に「何のために学ぶか」を説明することです。これを教え込むことさえできれば、授業は冒頭ながら8割方終えたようなものです。
大学の授業って、基本そうですよね。世間的にレベルが高いと言われている大学の学生達は、最初の授業でその学問の内容と意義を聴きさえすれば、その後多くは自分で勝手に勉強していきます。おまえの下手くそな講義を聞くより、自分で勉強した方が早いとね。ただし、私は丁寧にしているつもりですよー。
意義さえ分かれば、以後出遭うどんなに難しい内容でも耐えてこなすことができるでしょう、逆に分からなければ、ただ苦しいだけの道程が待っています。
昨年度の授業評価からは、「試験でヤマが外れた」、「暗記系で学ぶ意味がない」、「難しい」などなど、こちらの本意ではない散々な意見を頂きました。至極残念です。公式を丸覚えでは教育ではないだろうと、数式展開を一から詳しく説明してきたのに、暗記系科目だと解釈されたのは、全く心外なところです。
俯瞰してみると、今はコロナ世代が学校の中心にいます。遠くない昔ではありますが、コロナ時代はオンラインが常でした。有明高専ではシステムの完備に努めていましたが、設備のままならない環境の学校では、オンラインさえもままならなかったと思います。つまり、学んでいないということです。
世の中には、オンラインシステムさえ完備すれば、教員数を削減すなわち人件費を削減して教育を効率化できると主張する人達がいます。しかし事実はどうでしょうか。学生達の学力は明らかに落ちています。コロナ禍によるオンライン授業とは、教育を効率で図ることが如何に愚かなことかが証明されたという結論が得られた壮大な社会実験だったのではないでしょうか。
学ぶすなわち勉強とは、そもそも難しいものです。だから学び得た者は他者にはない武器を有し、社会で評価されるのです。だから保護者は、安くないお金を払って自分の子供達を勉強させるのです。難しいから、皆で集まって勉強し学び合うのです。教授方法が板書からスライドへと表面的に移り変わってきたといえども、学ぶ本質は今も昔も何一つ変わってないと思います。かつ今後も変わっていくものではないと思います。学ぶとは、YouTubeの視聴などで気軽に達成できるものではありません。
コロナ禍中を経験した学生さん達は、ある意味被害者だったでしょう。しかしながら、その立場に甘んじていたら、やがて彼らは社会から見放されるでしょう。昔の全共闘世代、そしてバブル世代が、その後下の世代から突き上げられたように。後生畏るべしです。そんな彼ら、しかしまだ若い彼らが自分自身の足跡を見つめ直す機会を得ることを祈るばかりです。
というわけで、コロナも明けて過去のものとなりつつある今年度の授業では、「学ぶ意義」の説明に改めて力を入れています。そしたらある学生さんの感想に、「説明を受けて本気で学ぼうと思った」とありました。頼もしい限りです。
Views: 97