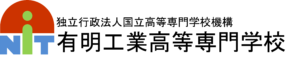12/21(土)は、博士後期課程時代の研究室である大阪大学 大学院基礎工学研究科 中戸 義禮研究室の同窓会でした。コロナ前の前々回以来7年ぶりの対面の会となりますので(前回はオンライン)、とても楽しみにしていたんですが、前日19(金)に風邪でダウンとなりました。大阪まで行ける体力もなく、残念至極でした。切符も払い戻ししました。不覚この上なしでした。
幸いオンラインで参加できましたので、画面を通じて皆様にご挨拶できました。中戸研の同窓会は約3年毎に行ってきており、今回が4回目でした。先代教授の故坪村 宏先生からのメンバーを含みますので、基礎工の第1期生(中戸先生もそう)から始まる幅広い年代で構成されています。
ただし通常の同窓会と違って、中戸研の同窓会はパーティー形式ではなくて、セミナー形式です。諸先輩方のご講演の後に学食でちょっとしたものはありますけど。登壇される諸先輩方は、無論、この社会で名を上げた大物ばかりです。私もいつかはこの舞台に立てるような実績を上げたいなと思う次第です。登壇のレベルは、私の中では最高峰に位置します。どんな国際会議も相手にはなりません。
Continue readingViews: 57