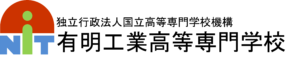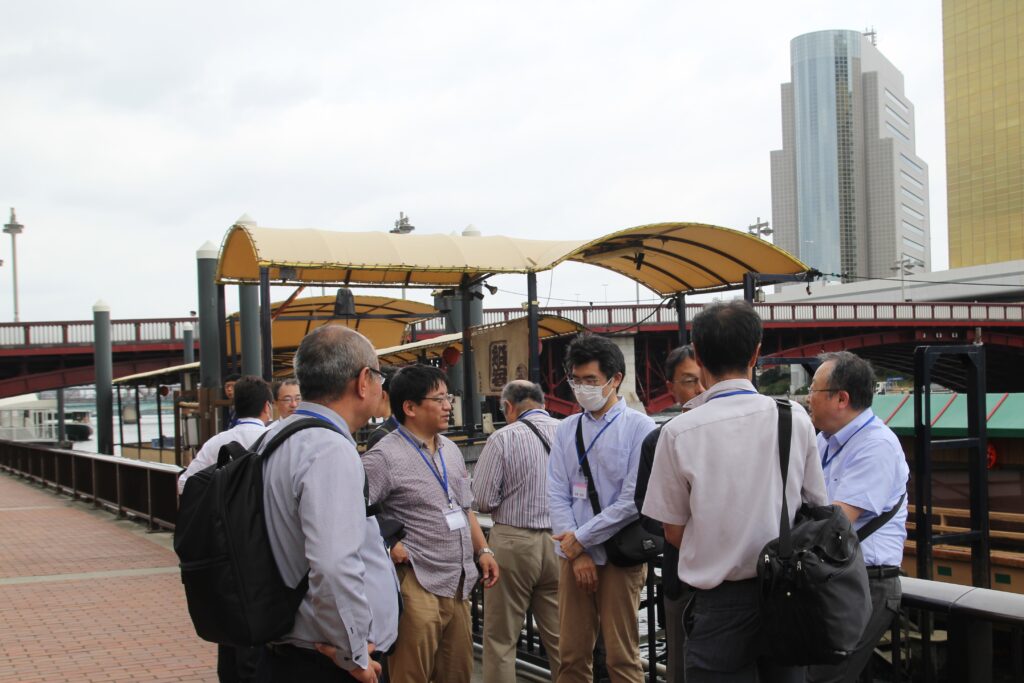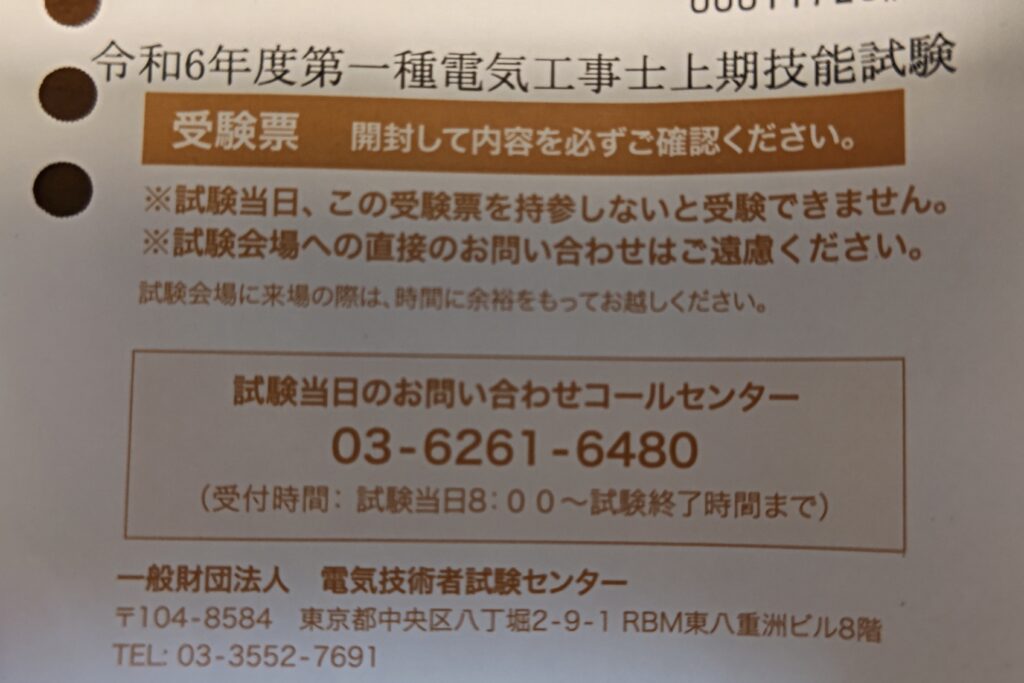高専(National Institute of Technology)は高等教育機関の一つですから、大学と同じように卒業研究が科目として存在しています。言い方を変えますと、高等教育機関であることは研究活動によって担保されています。
つまり高専は、研究機関としては大学/大学院や国研と同等なのですが、そこはやはり規模の問題がありまして、建物一棟に及ぶような大型実験装置はありません。一校全体で1,000人程度の学生数です。国立大学は一「学年」で3,000人を越す規模ですからね。私立大学だと10,000人規模にもなります。でも予算手当てとしては規模の割には大きくて、大学の先生方からは羨ましがられていることもまた事実です。実感ないけど・・・。
現在の研究室専攻科生達は、賞を取りまくってくれています。ちょっと取りすぎかなあと思い、この状況は後輩達へ続いてはいかないだろうなと、嬉しいようでちょっぴり不安な心持ちです。
この状況の見方を変えてみれば、マネージメントさえしっかりすれば、高専は十分な研究機関として機能することの証左でもあります。しかし残念ながら、現実はそうではないです。
Continue readingViews: 102