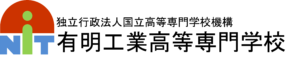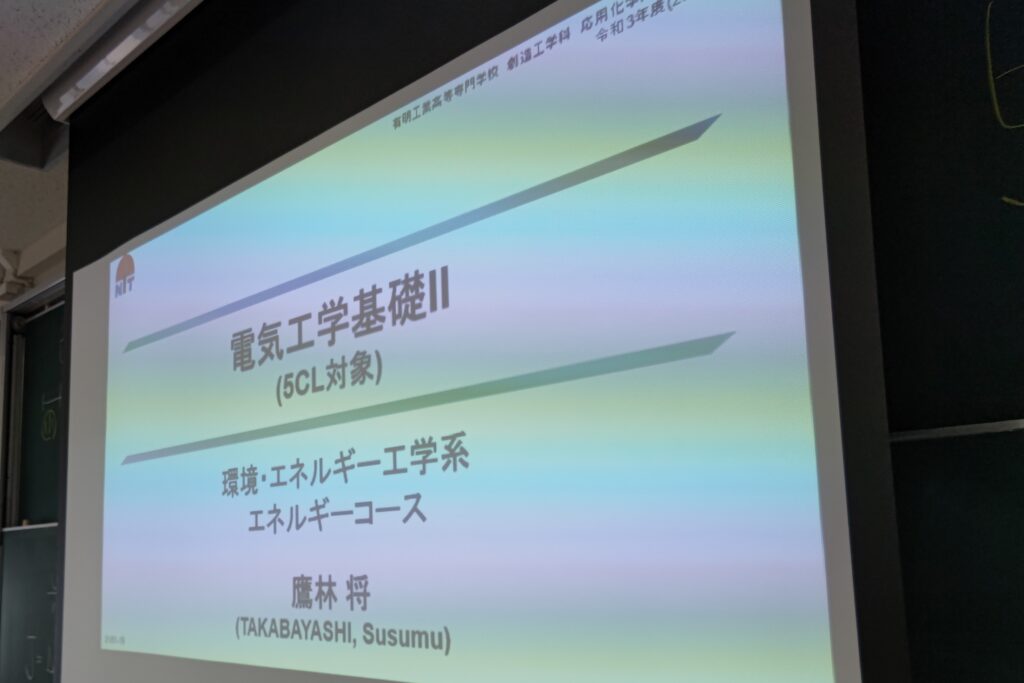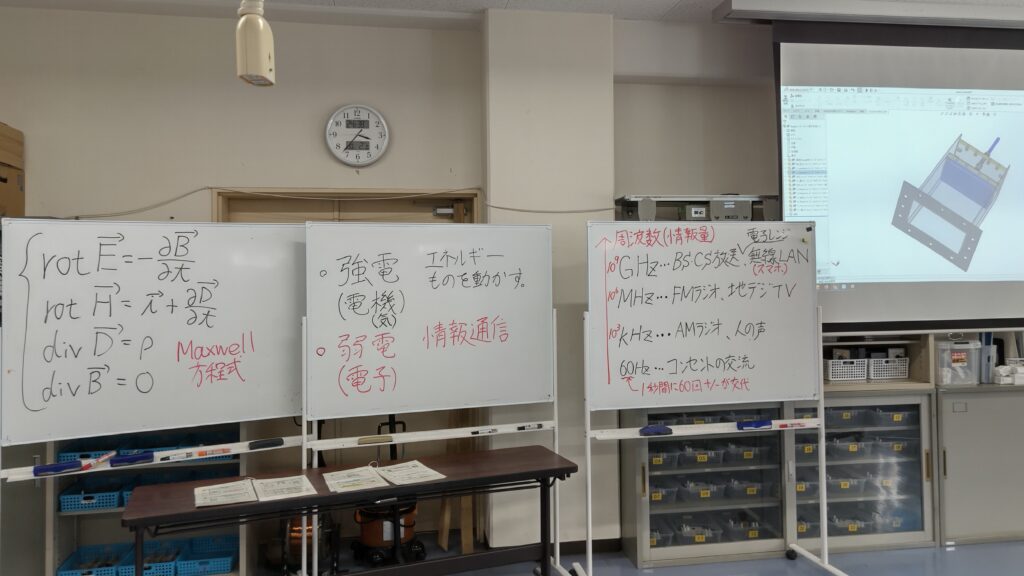人間は組織的な動物です。必ず何らかの組織に属しています。小さいのは家族から、大きいのは国家まで。複数に跨がって。学校や会社など中規模の組織に参加することを表す英語の動詞には、enterとjoinがあります。例えば、学校に入学するときはenterを使い、部活に入るときはjoinを使います。じゃあ会社に入るときは? 答えは、joinです。
権威ある辞書であるOxford English Dictionaryに依りますと、
enter: to become a member of an institution
join: to become a member of an organization, a company, a club, etc.
という意味となっています。どちらも似たようなものですね。でも、enter schoolとは言いますが、enter the schoolとは言いません。join the companyとは言いますが、join companyとは言いません。theがないのは、具体的な枠のない「機能」を表します。theがあるのは、具体的な枠のある「入れ物」を表します。enter the schoolを敢えて使うなら、それは校舎の工事業者さんなどか言うことですね。学校は工事現場の一つに過ぎないということです。
つまり、enter schoolは学校教育(という機能)に参加する、すなわち入学するという意味になるので、受け身の学生の立場となります。一方、join the comapnyは会社という人の集団に参加するので、自身は対等なメンバーの一員となります。
Continue reading →Views: 255